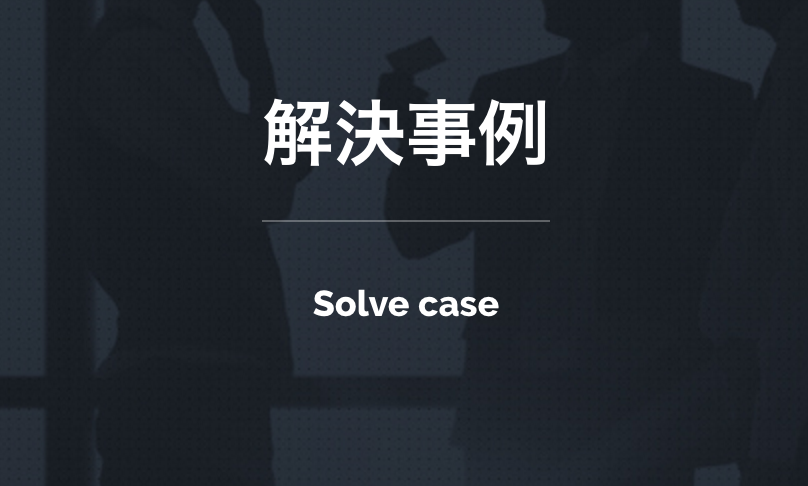店舗の立退きを求められ、多額の立退料を取得した事例
☓ 相談前 相談者は自宅兼事務所として事業されている方でしたが、①建物の老朽化と②他の事業に使うことを理由に賃貸人が立退きを求めてきたため、立退料を請求したいとのことで相談に来られました。 ◯ 相談後 賃貸人との任意の交渉では妥協点を見つけることができず、結局訴訟になりました。 訴訟では、裁判所が選任した不動産鑑定士らによって立退料が算定されましたが、依頼者の納得のいく金額ではありませんでした。 そのためこちらの依頼者側の選任した不動産鑑定士に依頼し、必要な意見書等を書いてもらい、証拠として提出した上で、裁判所が選任した不動産鑑定士の見解には、重要な点において問題があること等を裁判において主張しました。 その結果、当方の意見書の内容が概ね受け入れられ、移転費用はもちろんのこと、営業損失等についても損害として認められ、希望していた立退料を取得することができました。 弁護士からのコメント 不動産に関連する紛争、訴訟においては、必要に応じて弁護士のみならず他の専門家と協働して、専門的な見地からのアドバイスを頂くことも重要です。この件でも、依頼者側の不動産鑑定士が効果的な意見書を作成してくれたことから、良い方向での解決に結びついたといえます。 弁護士:中山和人